「ペーパー試験とネット試験(CBT方式)どちらを受けようか迷っている」
「ネット試験(CBT方式)の概要を知りたい」「ネット試験(CBT方式)のコツや注意点を知りたい」
ネット試験(CBT方式)を計3回受験の末、2021/8/3に合格しました私が、従来のペーパー試験とは異なる点/ネット試験(CBT方式)ならではの点について、コツ・注意点などを交えて解説したいと思います。
ペーパー試験とネット試験(CBT方式)の両方を受験した私だからこそ分かる点を、出来る限り分かりやすく解説しておりますので、ネット試験(CBT方式)の実態がよくわからず不安な人は、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次
はじめに

ネット試験(CBT方式)とは
■ ネット試験(CBT方式)は、「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」の略称で、従来から実施されているペーパー試験ではなく、コンピュータを使った試験方式であり、2020年12月から導入されています。
■ 試験会場となるテストセンターは全国に数百か所あり、1年間(一部休止期間あり)を通じて好きな日時で受験可能です。(3日前までなら日時変更が何回でも可能、また不合格になった場合は翌日から再予約の操作可能であり最短4日後に再受験が可能 ※例:8/1の試験で不合格の場合、8/2にPC・スマホ上で再予約の操作、最短で8/5に再受験可能)
■ 日商簿記では、2・3級がネット試験(CBT方式)に対応しています。(1級は対象外)
■ 2級、3級をそれぞれ個別で申込して、受験することも可能です。ただし、同一日に同じ級を重複で予約、また、同じ級を複数日で予約をすることはできません。
■受験料は2級:4,720円(10%消費税込)、3級:2,850円(10%消費税込)です。※事務手数料(550円(10%消費税込))が別途発生します。
■ 試験終了後にスコアレポートが配布されます。合格者のみ、スコアレポート内のQRコードからデジタル合格証が取得可能となります。
■ 以下、CBTリンク先 (初めての申し込みの場合、マイページアカウントの登録が必要です。)
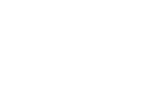
ペーパー試験との違い
以下一覧にまとめてますのでご参照下さい。
※ちなみに、合格(証明)の価値に関して、優劣は無いようですのでご安心を・・・
| ペーパー試験 | ネット試験(CBT方式) | |
| 試験時間(※1) | 120分 | 90分 |
| 試験時期(※2) | 指定時期 年3回(毎年2/6/11月) | 任意時期 |
| 試験場所(※3) | 各商工会議所指定の受験会場 | 任意のテストセンター会場 |
| 試験資格 | 誰でも受験OK | 同左 |
| 受験料 | 4,720円(10%消費税込) +事務手数料(550円) | 同左 |
| 試験科目 | 商業簿記(60点) 工業簿記(40点) | 同左 |
| 合格基準 | 70/100点 | 同左 |
| 解答方法 | 解答用紙に記入 | PCの解答画面に入力 |
| 筆記用具 | 持ち込みOK | 持ち込みNG (電卓のみ持込みOK) |
| 合格発表タイミング(※4) | 一定の据置期間経過後 (約2週間後) | 試験終了後即時 |
| 合格詔書の種類 | 紙の証書 | デジタル証書 |
■ 試験時間(※1)
・ペーパー試験 :120分
・ネット試験(CBT方式):90分
⇨ネット試験(CBT方式)は、ペーパー試験に比べて30分試験時間が短くなっています。ちなみに問題数は変わりませんが、ネット試験(CBT方式)では仕分け問題の勘定科目などもドロップリストの選択式で選ぶことが出来ますし、ペーパー試験に比べ比較的簡単な数値が多い印象ですので、試験時間が足りないということは、私個人としてはありませんでした。
■ 試験時期(※2)
・ペーパー試験 :指定時期(年3回、毎年2月/6月/11月)
・ネット試験(CBT方式):任意時期
⇨ネット試験(CBT方式)では、好きなタイミングで申し込み、好きな日程で受験することが可能です。また試験会場によっては、平日19:30からのスタートも出来ますので、忙しい社会人の方でも、早めに仕事を終えて、平日にサクッと受験するといったことも可能です。
■ 受験場所(※3)
・ペーパー試験 :任意のテストセンター会場
・ネット試験(CBT方式):各商工会議所指定の受験会場
⇨ネット試験(CBT方式)では、試験時期と同様に、好きなテストセンターで受験可能です。
■ 合格発表タイミング(※4)
・ペーパー試験 :一定の据置期間経過後(約2週間後)、施行商工会議所ごとに発表
・ネット試験(CBT方式):試験終了後即時
⇨ネット試験(CBT方式)では、試験終了後すぐ結果が分かりますので、ヤキモキしながら結果を待つということはないですね。
試験の流れ
■ 受験時刻の30分~5分前に受験会場に到着が必要。(5分前迄に到着しないと受験不可)
⇨余裕をもって30分前に到着することをおすすめします。ちなみに私は、30分前に到着し、試験開始時間を待つことなく、前倒しで試験開始することが出来ました。
■ 試験会場到着後、受付にて手続きを行う。
⇨受付の方に、自分の名前を伝え、本人確認証を提示すればOKです。その後、受験時の注意事項について確認がありますので、問題なければ、同意書に署名します。(受験票の事前郵送などはなく、マイページのIDパスワードの控えは不要でした。)
■ 携帯電話や上着などの私物を全てロッカー等へ保管(電卓のみ持込み)
⇨受付完了後、筆記用具/メモ用紙/その他注意事項の紙などを渡されます。その後、受付の方の指示に従い、電卓を除く全ての私物をロッカーにしまいます。
私は2つのテストセンター会場で受験しましたが、場所によって対応が少し異なりました。例えば、身分証明書は席に置いておくよう指示があった会場/指示が無かった会場、また、ロッカーも鍵式のところ/番号式のところなどの違いがありました。(余談ですが、番号式のロッカー会場は、もちろん試験官がロッカー開錠の番号を知っているので、不安性の私としては、試験中に私物が盗まれないか少し心配でした笑)
■ 受験方法の説明後、試験室へ入室。その後、指定の席に着席し、案内に従い試験開始
⇨席は指定されていると思いますので、指定された席に座りましょう。席に座った後、試験画面にいくつか項目(簿記試験、漢検・・?など)が表示されていますので、「簿記試験」の項目を選択し、受付の際に渡されたID/PWを入力後、注意事項に同意、最後に「試験開始」をクリックすれば、試験が開始されます。
■ 試験終了後、「印刷」ボタンをクリックし、終了。退出して、受付にて試験結果の紙をもらう
⇨試験時間が終了すると、自動で解答結果が集計され、その場で合否が分かります。「印刷」の画面が出てきますので、合否に関わらず、「印刷」のボタンをクリックして、退出します。退出しましたら、受付にて試験結果を紙で受け取ることが出来ます。(尚、試験の残り時間は、PC画面下に常に表示されています。もし制限時間前に終わりたい場合には、「試験終了」のボタンがありますので、それをクリックすれば、自動で自動で解答結果が集計されます。)
■ 合格していた場合、試験結果の紙にあるQRコードを読み取り、デジタル証明書をダウンロード
⇨これが合格の証明書になりますので、受付でもらう紙は無くさないようにしてください。
当日の持ち物
当日の持ち物は、以下3点です。(2021/8/3時点)
①電卓(そろばんはNG)
②身分証明書
③マスク(着用)
試験での注意点
■ メモ用紙/マウス/電卓のポジションを試験開始前に整える
⇨試験開始する前に、先ずは、メモ用紙/マウス/電卓ポジションを整えることをお勧めします。私は、1回目に受験した際、先に試験開始してしまい、その後少しあたふたしてしまい、時間をロスしました。
■ 雑音は少なからずあり
⇨試験室は、学校のPC室のようなイメージで、いくつもPCがあり、それぞれの席がパーティションみたいなもので区切られておりました。ただ、随時試験室には人が出入りし、また時折試験官の声も聞こえますので、神経質な方はもしかしたら気になるかもしれません。(ちなみに、私の受験会場ではどこもヘッドホンが置いてありました。)
■ “0”の桁数の入力誤りに注意
⇨解答はもちろんPCでの入力になるのですが、例えば、”12,500,000″を入力したいとした場合に、何回”0″を押せばいいか最初戸惑いました。千、百万単位での”カンマ(,)”は自動で表示されますので、打ち間違いがないか注意しながら進めましょう。
■ 入力単位に注意
⇨これはペーパー試験にも共通かもしれませんが、問題用紙と解答用紙の単位が異なることがあるので、その点はよく注意しながら解きましょう。私の場合、第二問で「株主資本変動書」の問題が出ましたが、問題では”円単位”だった一方で、解答用紙では”千円単位”の指定がありました。単位指定の認識が誤ったまま進めてしまいますと、全問不正解になってしまう可能性もありますので、お気を付けて・・・
ネット試験(CBT方式)を3回受験してみた感想
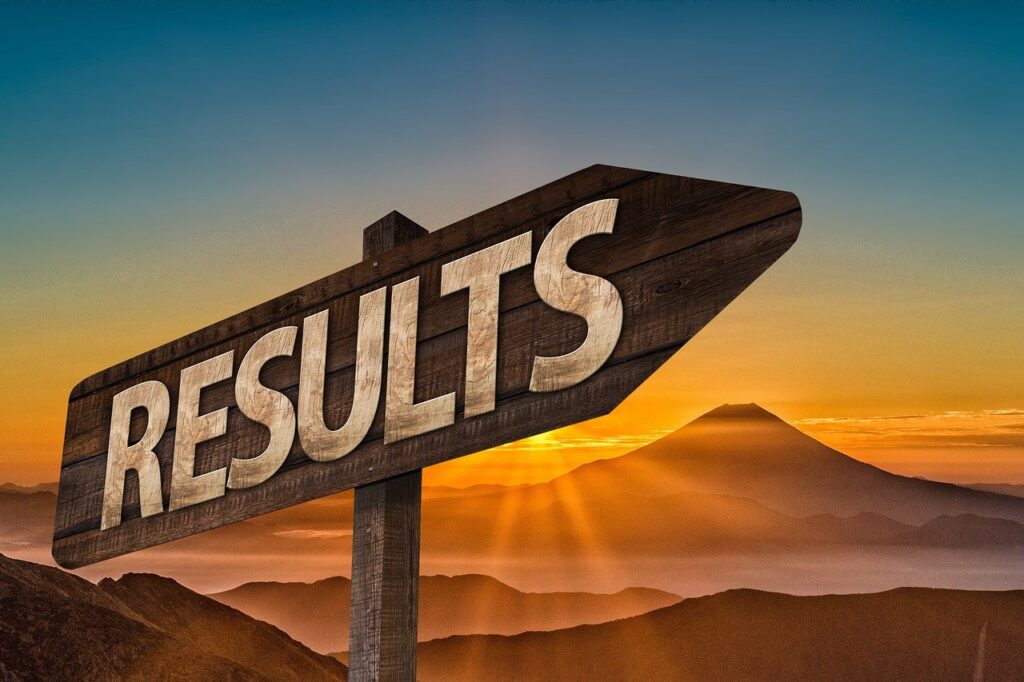
私の結果
私のネット試験(CBT方式)の受験結果は以下の通りでした。
・1回目(2021/7/25):67点/70点満点 *不合格
・2回目(2021/7/30):54点/70点満点 *不合格
・3回目(2021/8/3) : 85点/70点満点 *合格
- 第1問:16/20点. *各仕訳
- 第2問:20/20点 *株主資本等変動計算書
- 第3問:16/20点 *財務諸表の作成
- 第4問:24/28点 *個別原価計算
- 第5問:9/12点 *CVP分析

※合格すると、上記のようなデジタル合格証書が貰えます。
⇨上記の通り、約10日間の間に3回受験の末、合格しました。(ペーパー試験で不合格になると次の試験まで4ヶ月近く空いてしまいますが、ネット試験(CBT方式)だとすぐにリトライできるのが最大のメリットです)
ちなみに、3回の受験結果の点数が、最大で30点近く開いていますが、これは自分の得意な分野が出たか/不得意な分野が出たかの違いだと感じています。私自身、会社員をしていますが、この3回の受験期間の間は、仕事が多忙で、勉強時間が極端に削られていましたので・・・
もちろん、全分野を完璧にマスターできればベストですが、社会人の方など忙しい方は、受験回数を重ねて、自分の得意な回に当たるまで受験し続けるというのも時短テクかもしれないです。(但し、その分費用はかさんでしまいますが笑)
また、3回目に受験した際、第3問にて「株主資本変動書」の問題が出たのですが、1回目に受験した際にも同じような問題が出ていたので、第3問は満点を取ることが出来ました。このようにもしかしたら、回数を重ねるごとに、同じ形式の問題に遭遇し、合格への確率を上げることにも繋がるかもしれません。
ペーパー試験とネット試験(CBT方式)どちらが簡単か
私は、圧倒的にネット試験の方が簡単だと思いました。
理由は以下の2つです。※あくまで私個人の意見ですので、ご参考までにお願い致します。
①問題内容/計算プロセスがペーパー試験に比べ簡単
⇨よく考えてみてください。ペーパー試験が120分であるのに対し、ネット試験は90分です。問題数が変わらないのに試験時間が違うということは、同じ難易度で設定しませんよね。つまり、試験時間が短いということは、ネット試験(CBT方式)の方が簡単であるということです。私自身、どちらも受験した経験がありますが、圧倒的にネット試験(CBT方式)の方が簡単だと思いました。例えば、ネット試験(CBT方式)で連結会計が2度出題されましたが、連結会計の中でも難しいとされる”アップストリーム”の論点は見かけませんでした。また、計算方法もそこまで手こずるものはありませんでした。本当に基礎を押さえているか、がネット試験(CBT方式)攻略の鍵だと思います。
②科目はプルダウンにて選択
⇨ペーパー試験では科目を自分で記入(場合によっては記号記入)しますが、ネット試験(CBT方式)ではプルダウンで選択します。そのため、ネット試験(CBT方式)では、正式名称/漢字を忘れたということもないですし、またペーパー試験に比べ少ない数の選択肢から選ぶため、混乱も招きにくいです。
ネット試験(CBT方式)は今が大チャンスである理由
⇨昨今、簿記2級はどんどん難易度が増しており、中には「1.5級だ」という方もいらっしゃいます。
特に連結会計が試験範囲に追加されて以降の難化は激しいです。
そんな中で、ネット試験(CBT方式)が2020年12月に導入されてますが、受験者ごとに異なる問題が検定出題範囲からランダムに出題される形式であり、基礎に忠実な問題ばかりが出題されています。
そのため、これまで中長期で勉強していた人も、短期で合格することは十分可能となっています。
今後、ネット試験(CBT)がどうなるのか(より難しくなる、廃止になる、等)の展望は分かりませんので、今のうちにネット試験(CBT方式)を受験しておくことを強くおすすめします!
合格するための勉強方法/コツ

簿記2級の問題構成/出題内容
簿記2級の問題構成/出題範囲は以下のようになっており、100点満点中70点が合格基準です。
■ 第1問 【配点20点】
⇨商業簿記の仕訳問題(5問)
■ 第2問 【配点20点】
⇨連結会計(連結精算表・連結財務諸表)、株主資本等変動計算書、銀行勘定調整表、固定資産/有価証券/現金預金/商品売買/リース取引の問題、理論問題、等
■ 第3問 【配点20点】
⇨財務諸表、精算表、本支店会計、等
■ 第4問(1)【配点12点】
⇨工業簿記の仕訳問題(3問)
■ 第4問(2)【配点16点】
⇨総合原価計算(単純・工程別・組別・等級別)、個別原価計算、部門別計算、標準原価計算、等
■ 第5問 【配点12点】
⇨直接原価計算、CVP分析、標準原価計算(差異分析)、等
試験対策/コツ
■ 問題を解く順番/時間配分のおすすめ (私個人の意見ですのでご参考まで)
第1問(10分)⇨第4問(20分)⇨第5問(10分)⇨第2問(25分)⇨第3問(25分)
⇨先ずはサクッと第1問の商業簿記の仕訳を解き、その後、第4・5問の工業簿記の問題、最後に比較的時間のかかる第2・3問の商業簿記の順に解いていました。上手くいけば、最後に見直しの時間が余りますが、基本は、見直しの時間が余らないものと想定し、各問題ごとに確実に潰していくことを意識していった方がいいいです。とはいえ、試験時間も90分と短いですので、もし苦手な問題が出たら後回しにして、苦手なところは最後に解き、部分点をとっていくイメージがいいでしょう。
■合格に向けた戦略/コツ
私は各第問ごとに以下の目標点を掲げて勉強していました。
- 第1問(16点/20点)
- 第2問(12点/20点)
- 第3問(12点/20点)
- 第4問(24点/28点)
- 第5問(12点/12点)
⇨ポイントとして、とにかく仕訳を最重要視しましょう。なぜなら、純粋な仕訳問題(第1問、第4問(1))だけで配点が32点近くあり、合格は70点以上のため、仕訳のみで、合格点の5割近くを占めることになるからです。加えて、第2・3問も仕訳の知識が必須となるため、簿記2級に関しては、仕訳を確実に押さえることで、合格にグッと近づくと言えるでしょう。
⇨また、工業簿記(第4・5)は9割~満点を目指しましょう。工業簿記に関しては、簿記2級から初めて登場したものですので、感覚としては、商業簿記(第1~3問)よりも基本に忠実な簡単な問題が出ていることが多いからです。
役に立った参考書/アプリ/動画
(1)みんなが欲しかった! シリーズ (日商2級 商業簿記/工業簿記の教科書+問題集) *計4冊
こちらは、TAC出版の「みんなが欲しかった簿記」になります。
簿記2級に関しては、①商業簿記-教科書、②商業簿記-問題集、③工業簿記-教科書、④工業簿記-問題集の計4冊をメインに勉強しました。教科書では、図解を用いて分かりやすく解説されているため、初心者/独学者でも使いやすいのではないかと思います。内容に慣れてきたら、問題集でひたすら、演習しましょう!(教科書/問題集の中に発展項目がありますが、私は飛ばしてやってましたので、時間がない方は飛ばして良いと思います)
(2)スッキリうかる日商簿記2級 本試験予想問題集
「予想問題9回分 」+ネット試験の模擬試験プログラム付きの予想問題集です。私は、これをとにかくやり込みました。特にネット試験の模擬試験プログラムは、絶受験前に一度受けておくことをおすすめします。PC操作など、少し慣れが必要になるので、本番で慌てふためかないよう、万全に挑みましょう!
(3)パブロフ簿記2級商業簿記

こちらは、商業簿記の仕訳を勉強できるアプリです。
ちょっとした隙間時間や電車での移動時間などで活用することができるので、かなり重宝していました。間違えた問題のみ出題したりもできるので、試験直前の復習にはとても便利です!
ちなみに工業簿記もあります。私は購入しましたが、商業簿記に比べ少し使いにくいイメージでしたので、ほとんど使用しませんでした。
(4) 【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆき
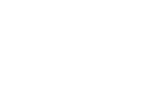
簿記2・3級の内容に関して動画でわかりやすく解説してくれています。私自身、散歩しながらなど、ふくしまさんのYoutubeを観ながら学習させてもらいました。正直かなりクオリティが高く、本当に予備校顔負けレベルです・・・
もし、参考書での勉強が苦手という方いらっっしゃれば、先ずは動画で勉強を進めてみるというのも良いかもしれません。
費やした時間/費用
結論、約1ヶ月(7/4勉強開始、8/3合格)、勉強時間は約100時間、費用は約4万円でした。
必要時間はスタート時点の知識、また、独学/通学どちらを選択するかで大きく変わってくると思います。一般に、簿記3級保持者が、2級に合格するまでに必要な勉強時間は、独学なら4~6カ月(250~350時間)、通学・通信講座なら2~4カ月(150~250時間)と言われています。
私は、3年前に、簿記2級の参考書を購入し2週間勉強の上、ペーパー試験を受験したことがありました(当時のスコアは24点/100点で不合格、3級はこれまで受験経験なし)。また、仕事柄、財務諸表や貸借対照表は普段から目にしていましたので、比較的知識をもって勉強を開始しましたので、その点は比較的早く合格できた方かと思います。※重要なのは個々人の知識にあった無理のない計画で勉強することでしょう。
私は会社員で平日はあまり時間が無かったので、目安として、平日3H、土日9H勉強していました。(平日は出社前に1Hカフェで勉強し、会社の昼休みは30分を勉強に当てました。)もちろん無理のない範囲で勉強すべきですが、ダラダラと中長期で勉強するよりは、短期集中でモチベーションが下がらないうちにガッツリと勉強した方がいいと思います!
また、私は短期で合格したかったので、基本は問題集を中心に解きまくっており、わからないところは都度、教科書を見て確認するスタイルで勉強していました。(以下、勉強時間配分/スケジュール/費用内訳の詳細です)
■ 勉強時間配分
- 商業簿記(20H)
- 工業簿記(20H)
- 総合演習(60H)
■ スケジュール
- 第1周(~7/11)
⇨工業簿記の問題集を1周 (分からなくても1週することを意識、発展問題は飛ばす)
⇨商業簿記は、パブロフ簿記アプリを1周
- 第2周(~7/18)
⇨商業簿記の問題集を1週(分からなくても1週することを意識、発展問題は飛ばす)
⇨工業簿記は軽く2週目、息抜きがてらパブロフ簿記アプリで勉強
- 第3周(~7/25)
⇨演習を6回分実施 ※復習含め
⇨息抜きがてらパブロフ簿記アプリで勉強
- 第4周(~8/3合格まで)
⇨計3回ネット試験(CBT方式)を受験、間違えたところを中心に復習
⇨苦手部分を個別に確認
■ 費用内訳(計 約4万円)
- 参考書/問題集:約1万円
- ネット試験(CBT方式)受験料3回分:約1.5万円
- その他(カフェ代/交通費):約1.5万円
おわりに

今回、簿記2級のネット試験(CBT方式)について、私の経験を踏まえ解説させて頂きました。
簿記2級は、基本に忠実に勉強さえすれば、誰でも取得可能な資格だと思います。その一方で、就活や転職では重宝されるコスパの良い資格ですので、簿記2級受験を悩まれている方がいらっしゃいましたら、是非チャレンジすることをおすすめします。
以上の内容が、皆さんの簿記2級の合格に向けて、少しでも何かのお役に立てれば幸いです。


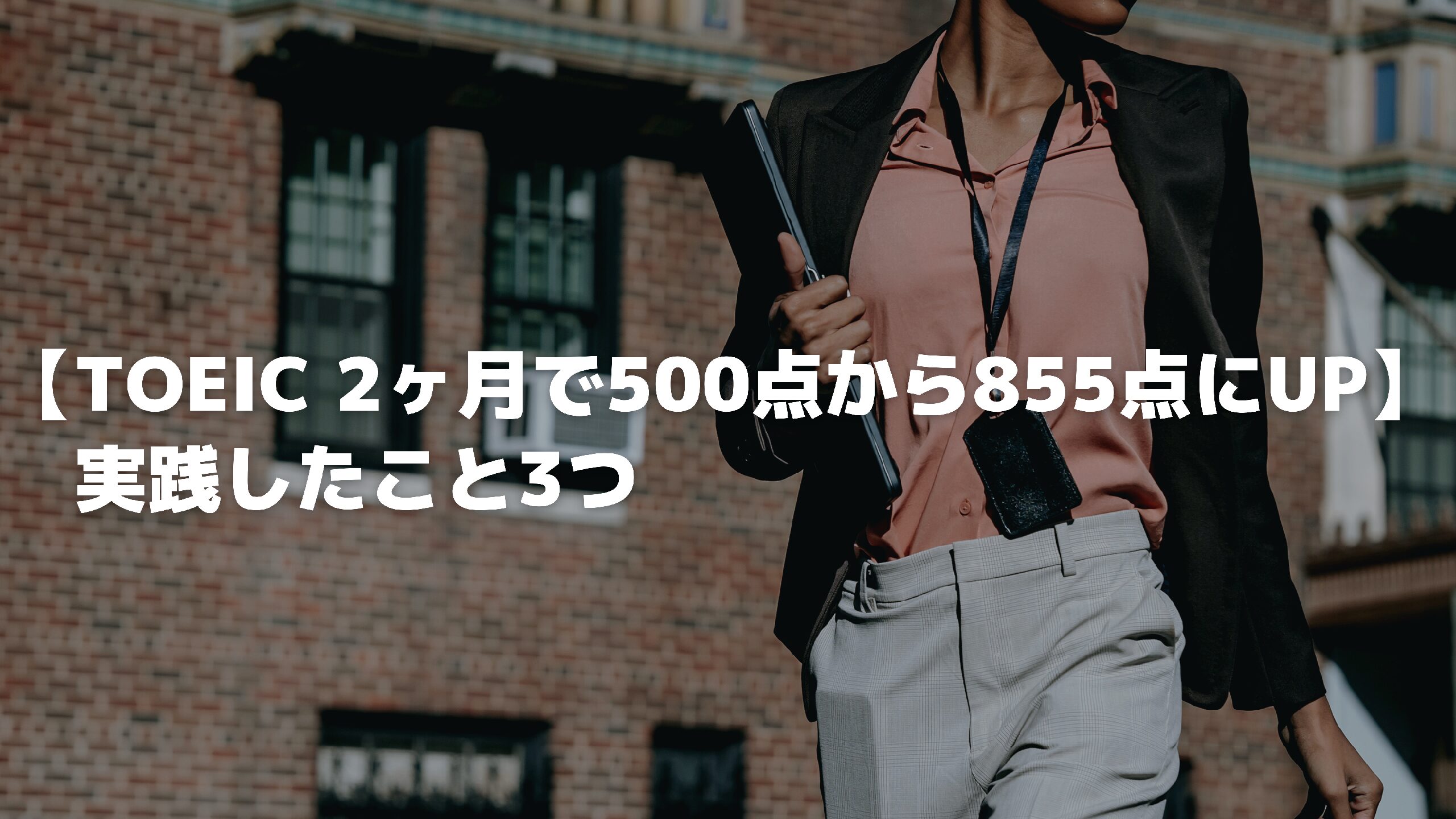
コメント